人材育成の重要テーマとして、3つの人材タイプを定義しています。先行きが不透明で将来の予測が困難な変化の激しい時代には、迅速な意思決定ができ、変化に柔軟に対応できるリーダーシップをもつ「グローバル経営人材」。これまで、ゴム技術を基盤として社会にイノベーションを起こしてきたように、これからも新しい価値を提供し続けられる「イノベーション人材」。デジタル技術を活用し、より高度で効率的な意思決定や業務推進に加え、ビジネスに応用し、新たな価値を創出できる「DX人材」。これらの人材の継続的育成に努め、企業価値を向上させていきます。
変化の激しいVUCAな時代には、柔軟性と迅速な意思決定が求められます。そのため、不確実な状況下でも冷静に判断し、先見性を持って行動できる「グローバル経営人材」の育成が極めて重要です。
あわせて、チームを効果的に率い、変化に柔軟に対応できるリーダーシップも必要不可欠となります。
絶えず学び、自らを成長させることができる人材を育成できる仕組みを構築していきます。
住友ゴムはゴム技術を基盤として社会に新しい価値を提供するイノベーションを起こしてきました。現在でも新しい技術として「Smart Tyre Concept」「水素エネルギーを活用したタイヤ製造」「高減衰ゴムを活用した制振技術」などを生み出し続けています。これからも新しい時代にイノベーションを起こし続けることができるよう、イノベーションに挑戦できる人材と風土を育てていきます。
デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを根本から変革し、より高度で効率的な意思決定や業務推進をすることが求められています。この変革を成功させるためには、デジタル技術の知識だけでなく、ビジネスに応用し、新たな価値を創出できる能力や変化に柔軟に対応し、組織内でのデジタル化推進のリーダーシップを発揮することが求められます。こうしたDX人材を育成し、定着し、活躍できる仕組みを作り上げていきます。
2023年からイノベーション人材育成プログラムとして「イノベーションアカデミー」を開始。これまではアントレプレナーシップマインドの醸成を中心としたプログラムを運営してきましたが、2025年からはマインド醸成に加え、本格的なイノベーション創出のためのアイデア出し方法を始め、ビジネスモデル/新規事業創出のためのプログラムを拡充させ、「イノベーションアカデミー2025」としてブラッシュアップしました。“強い想い”と”果敢に挑戦”~その想いが未来をはずませる~を目的に、イノベーション人材育成と新規事業創出に向けた全社施策としてさらなる拡充を図っていきます。


2021年に管理職の人事制度を従来の職能資格制度から役割等級制度へ移行し、仕事基準で処遇を決定する仕組みを導入しました。これに伴い、管理職のキャリアパスを「マネジメントコース」と「スペシャリストコース」に分け、専門性を活かしたキャリア形成を可能にしました。
社員のモチベーション向上とイノベーションを促進し、チャレンジを推奨する風土づくりを目的とし、取り組みを表彰するイベントを開催しています。
表彰はテクノサイエンス賞・サステナビリティ表彰の2部門で行われます。
テクノサイエンス賞は、次世代への創造の芽を生み出す基礎研究・技術開発・設備開発・生産技術などにおける革新的な内容に対して表彰します。サステナビリティ表彰は、当社グループのマテリアリティ:重要課題の解決につながる取り組み、ありたい姿の実現に近づく取り組み、社会価値提供に貢献された取り組みを表彰します。
データに基づく意思決定を全社で実現するため、DXリテラシー教育を推進しています。DXに必要な3領域(ビジネスコア、プロ、データエンジニア)に対応した育成体系を構築し、2024年末までにスタッフ系全従業員約3,500名のDXリテラシー研修受講を達成しました。さらに、2024年5月からは知識・スキル・経験を証明するオープンバッジを導入し、e-learningに加え、実践的な学習機会を拡充させています。社内の専門講師の育成や社員同士の学び合いを促進し、個々の成長を組織の競争力向上へつなげる好循環の仕組みを作り上げていきます。
DX人材育成の一環として、PBL(課題解決型学習)を導入し、学びを実務に直結させる仕組みを強化しています。受講者は実際の業務課題をテーマに設定し、データ準備・AIモデル開発・アプリ作成などを通じて、実務に役立つ成果物の創出に取り組みます。これまでの取り組みで40件以上のPBL活動を進めました。今後はさらに、社員の主体性と創造性を引き出す仕組みを整備することで、学習の定着と価値創出を両立し、DX推進を加速させています。
当社では、定型的な事務作業の効率化を行い、より付加価値の高い業務にリソースシフトを図り、社員のデジタルリテラシーの向上に寄与することを目的として、RPAの活用を促進しています。社員が自らRPAツールを開発・活用できる環境を整備しています。プログラミング未経験からでも開発できるよう研修プログラムを提供しています。特に、e-learning形式のフレキシブルな研修やTeamsでの随時の質疑対応、社内の事例共有などのサポート体制を手厚くしています。2025年10月末までに595名が研修を受講完了し、857件のRPAユーザー開発が行われています。RPAユーザー開発とIT部門によるRPA開発を合わせると、業務時間が年間あたり10万7千時間削減され、より付加価値の高い業務に集中できるようになりました。さらに社員のデジタルリテラシーの向上にも寄与しています。今後もRPAの活用を推進し、さらなる業務効率化を図るとともに、社員のスキルアップを支援していきます。特に、AIとの連携を強化し、より高度な自動化を実現することで、企業全体の競争力を向上させることを目指します。
データの可視化による迅速かつ高度な意思決定を可能にする文化醸成を目的に、セルフBIツール「Tableau」の活用を推進しています。製造・SCM・販売・ソリューションなど幅広い部門で、レポート作成効率化やダッシュボード分析を通じて業務の高度化を実現しデータ活用文化の定着に寄与しています。文化を広めるために社内BIコンペティションや情報発信として社内ラジオ「Tab Talk」も定期開催し、社員が楽しみながらスキルを向上する機会を提供しています。さらなるデータドリブン文化を広めるため「DATA Saber」認定プログラムも導入し、2025年末までに30名が認定されています。
データドリブンな組織づくりを目的に、ナレッジ共有とユーザー同士のコミュニケーションを促進するイベント「Digital Innovation Day」を2022年から毎年開催しています。各部門・拠点でのDX活動を共有し、他社事例から学ぶことで、イノベーションにつながる新たな交流を創出。2025年は6月と10月に開催し、合計で約650名が参加しました。本取り組みは国内にとどまらず、中国やタイ拠点でも展開しており、グローバル全体でデータ活用文化を広げる重要な役割を担っています。今後もシナジー創出の起点として、継続的な開催を通じてDX推進を加速させていきます。
業務の生産性向上と高度化を目的に、生成AIの社内活用を加速させています。その一環として、社内勉強会「AI Café」を定期開催し、Copilotの基本操作から高度なプロンプト設計まで、レベル別に学べる機会を提供しています。実際の操作例や社内外の事例紹介を通じ、社員が安心してAIを業務に取り入れられる環境を整備。また、全社員対象の「生成AI活用アイデアコンテスト」を開催し、柔軟な発想による業務改善アイデアを募集。これらの取り組みにより、社員のAIリテラシー向上と業務革新を同時に実現し、DX人材の育成を加速しています。
役員層のリーダーシップ向上と一枚岩化を目的として、役員及び一部の海外法人のCEOに対し社外のエグゼクティブコーチによるコーチングを行っています。これに加えて、毎週配信されるエグゼクティブコーチからのリーダーシップに関するメールマガジンについて、各役員の受け止め、考えを共有することで、自身のリーダーシップを見直す機会を設けています。これは役員間での相互理解、連携強化にも繋がっています。
また、年1回は役員研修を実施しています。過去の住友ゴムの経営判断を題材に当時の状況を振り返り、その教訓を今後の経営に活かしていこうとしています。ここで活用した事例は、次世代経営人材育成のための教材としても活用予定です。

次世代経営人材育成のための選抜研修として「RISE Management Frontier 2025」を新たに開始しました。以前も同様の研修は実施していましたが、今年対象者の選抜方法及びカリキュラムを一新しました。今後の経営人材に求められる資質を再定義し、「多様性と変化を受け入れ、異文化の壁を超えて、人と組織を動かし、現場で信頼を築き、成果で未来を創る──人間的魅力と実行力を兼ね備えた“グローバル変革リーダー”」を育成することを目的とし、カリキュラムを見直しました。具体的には、経営の基本スキル、昨今の重要経営アジェンダの理解に加え、自社事例分析、他社の同階層社員との交流等を追加しています。
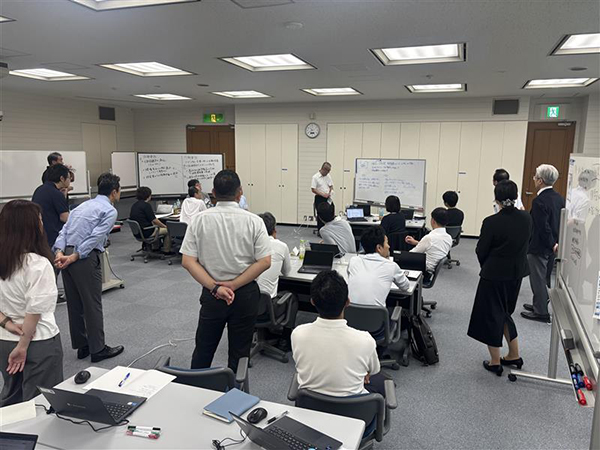
組織のマネジメント品質向上、管理職をはじめとする管理監督職のリーダーシップ行動の内省、成長支援、そして、健全な組織風土醸成による従業員エンゲージメント向上のため、360度フィードバックを毎年実施しています。360度フィードバック結果は、重要ポストへの任用時の参考情報としても活用しています。現在、住友ゴム本体と一部の国内/海外関係会社で実施していますが、多面的に人材を見て、将来の幹部人材を任用していく仕組みの構築を目指し、海外拠点でのさらなる拡大を進めていきます。
また、2025年より エンゲージメントサーベイ結果とのクロス分析も実施します。各管理職の発揮するリーダーシップと社員エンゲージメントの関係性を紐解き、組織全体の活性化に繋げていきます。
当社グループの人的資本経営実現をリードする人材の1つの人材ポートフォリオとして「グローバル経営人材」を掲げています。その人材ポートフォリオについて、役員で討議のうえ定義をしました。今後はその人材要件を明確にし、現在策定中のグローバルHRポリシーのうち、採用、人材育成、評価ポリシーに落とし込み、トレーニー派遣制度や海外ナショナル人材の拠点横断的な経験付与等も含め、人事施策のオペレーションに落とし込むことで、グループ全体のグローバルでの経営人材育成に繋げていきます。